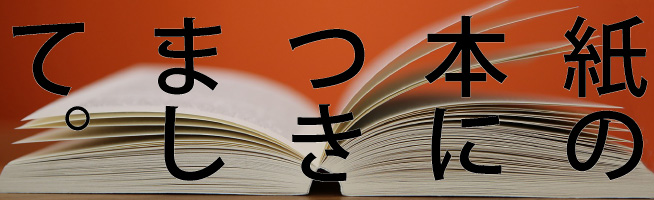ガタケット163にて配布したペーパーに合わせた小ネタです。
▽お手持ちでない方はこちらをどうぞ。(背景写真提供:たまこ様)

→印刷用PDF
夜風に揺れてくせのついた襟足が弾む。頬の輪郭が対岸の夜景の光で輝いて見えた。
「すっげ、さっすがデートスポット」
こんな肌寒い日でも沿岸にはぽつぽつと人影がある。大抵が二人組で、互いに距離を取って眼前に広がる景色を眺めていた。
風のお陰でちょっとはしゃいだぐらいじゃ離れたところにいる他人には声も届かない。街灯と対岸の光で明るいとはいえ、離れた場所に立つ人間の顔がよく見えるわけでもない。酔い覚ましの散歩場所としては悪くなかった。
行ったことがないからとここを選んだ二郎はそこまで考えちゃいなかったんだろうが、面倒な連中に声を掛けられることもなく静かに風と景色を楽しめた。
「写真撮っとこ……あ、ちっとブレた。やっぱスマホじゃ限界あるよな」
近くの欄干に肘を置いて何枚か撮影しては画像を確認してボヤく。コイツはSNSもやっているし、家の飯や家族や仲間の写真、アニメソフトのパッケージの写真なんかよくアップして、何でもかんでも仲間内で共有している。だけどそこに今日ここで撮った写真は投稿できないだろう。イケブクロのガキが夜のヨコハマで夜景を見て来たなんて言ったら誰と一緒だったのか追及される。ブクロからすりゃヨコハマは敵の縄張りだ。夜中に一人で来るような場所じゃない。
やっと満足いく一枚が撮れても隣にいる俺に見せて褒め言葉を要求して、賛辞と呼べるかどうかも怪しい雑な講評を受けて終わりだ。それでも満足した様子で携帯をポケットに突っ込んだ。
「……そんなに夜景がみたけりゃ今度その辺のホテルでも行くか?」
「家が遠いわけでもねぇのになんで泊るんだよ。こうやって近くまで来て空気ごと味わうのがいいんじゃん」
「まったくテメェは金のかかんねぇガキだな」
褒めたつもりはないのにニヤケ面で肩をぶつけてきた。
コイツはガキばっかりで貧しく育ったせいか贅沢に慣れていない。テリトリーバトルが始まってからは賞金や取材のギャラで貧乏からは脱したはずだが、アニメや漫画以外に金をかけている気配がない。夜のみなとみらいなんか行きたがるくせに高層階からの夜景だとかホテルだとか、そういうものに憧れているわけでもないらしい。定期的に会うようになってずいぶん経つが、ガキとは価値観が違いすぎて何をすりゃ心底喜ばせることができるのかは分からないままだった。
写真に飽きるとまばらに見える他の客が移動するのを見計らって少し歩いた。気温はそう低くはないが風にさらされて末端から冷える。しばらく観覧車の色の変化を数えていた二郎が「寒い」と言ったのを機に帰路についた。
ハマには珍しく静かな夜だった。歩くうちにだいぶ酔いが醒めてきたからコンビニに寄った。俺は酒、ガキは食い物。
「また飲むのかよ」
「テメェこそ晩飯たらふく食ったくせに燃費悪すぎだろ」
店内に入ったら早々に解散してそれぞれ目的の商品を物色する。
今日はいい気分だった。昼間も面倒な仕事はなく、天気も良くて夜には時間が空いたから二郎を呼びつけて高い肉を貪る姿を肴に晩酌をした。後はもう部屋に帰って適当な頃合いで眠れば近年稀に見る良い日で終われる。
そこに水を差すようにして店内のスピーカーからクソ野郎の声を流し始めた。先月の終わりにイケブクロ連中が新譜の配信を始めたからだ。有線放送の最新チャートチャンネルでは連日賑やかなガキどもの曲が垂れ流しにされている。いい気分にケチがついて舌打ちし、さっさと店を出ようと二郎の姿を探した。スナック菓子を物色していたと思ったらスピーカーに近い総菜コーナーに移動して曲に合わせて鼻歌なんか歌っている。苛立ちが三割増しだ。やっぱりゆっくり買い物なんかしていられない。
機嫌よく棚のラインナップを見ている背中に声を掛けようとした。そうしたら今度は電話だ。二郎はポケットから携帯を引っ張り出して着信に応じた。
「兄ちゃんどうしたの?」
元から天井の低い腹立ちゲージは一発で限界値に達した。
一応コイツは未成年だし泊りの連絡なんかは認めているが、今回はどうせくだらない用事だ。実際、二郎が俺に気が付いてマズイって顔をしながらも電話に向かって話していたのはアニメの録画の話だった。用件が済むと二郎は話を終える素振りを見せたが、一郎相手に強引に話を打ち切るまでは出来ない。何か言われて話を続けようとしたところで手の上から携帯を掴んで耳から引き剥がす。
「うおっ、なにすんだよ!」
「テメェこそ俺様の目の前でいい度胸じゃねぇか」
「ちょっと用があって喋ってただけだろ!?」
「用だ?女みてぇに長電話しやがって」
「長くねぇだろ、アンタが短気なのをこっちのせいにしてんじゃねぇよ」
気の短さにかけては二郎だってケジメつけさせられた後の小指みたいなもんだ。レジの向こうで店員がハラハラ見守る中、出入口を顎でしゃくった。むやみやたらに堅気のみなさんの商売を邪魔するもんじゃない。
店の外で手っ取り早く自分の立場ってものを教えてやるためにマイクを掴む。なにも一方的な加害じゃない。どちらかといえば二郎の方が嬉々としてバトルに乗り出すぐらいだ。テメェより遥かに強いのが分かっているヤクザ者に喜び勇んで喧嘩売るなんざ育てたヤツの気が知れない。
まあここで二郎が倒れたとしてもマンションはすぐそこだ。過剰な手加減は必要ない。一発シメてやろうとマイクのスイッチを入れた。
そうしたら今度はコンビニに前に通りかかって路肩に停まったワゴン車から頭の悪そうな連中が五、六人もぞろぞろと出てきやがった。
「おいおい、ホントに碧棺左馬刻と山田二郎じゃねぇか」
「有名人がほっつき歩いてるって聞いて来てみりゃ喧嘩かぁ?」
「いいところに居やがったな。俺ら左馬刻には恨みがあってよぉ、丁度いいから加勢するぜ」
声をかけておきながらちんたら歩きやがって。その辺の害虫でも移動ぐらい機敏にやってのける。
勘違い馬鹿どもは勝手に二郎のバックについた。その一人が馴れ馴れしく肩に手を置こうとして振り向いた二郎の肘をモロに食らってその場で二つ折りになった。だがそこで素直に頭を下げちゃいけない。膝を食らって完全に地面に転がる羽目になる。
二郎は手早く一人を沈めると服を掴もうとする手を避けて踊るような軽やかさでこちら側に移動した。
「マージしらける。何で俺がテメェらに助けられなきゃなんねぇんだよ」
「先に並べて転がしときゃ俺様とやり合って倒れた時のマットぐらいにはなるんじゃねぇか」
「ざけんな、倒れねぇからそんなもん要らねぇっつの」
まさか俺と二郎が組むなんて思わなかったんだろう。味方につけたら万に一つぐらいは俺に勝てるかと思った二郎が敵に回って雑魚どもがあからさまに狼狽え始めた。雑魚のやることはとことんダセェ。
やる前から結果は見えていたが、如何に能無し集団と言えども丸腰じゃなかった。集団の中の二人がヒプノシスマイクを取り出した。ベーシックな形状で、正規品か違法マイクかは判別がつかない。
「ぐちゃぐちゃナメたこと喋ってんじゃねぇよ!」
「勘違いすんなよ、これはテリトリーバトルじゃねぇんだ。要はコイツら二人潰せば俺らの勝ちだろ?」
マイクを持たない連中が折り畳みナイフを取り出し、これ見よがしに刃を開いた。ラップで勝てなくても物理攻撃でこっちのラップを妨害すればイケるだろうって腹か。
「おら、いくぜテメェら!」
ルールもクソもない。こっちの同意も待たずにマイクを起動してワンバース目が始まる。間合いをキープしてヒプノシスマイクを使う二人の脇からナイフを握った馬鹿どもが躍り出る。動きからして使い慣れているとは言い難い。大振りな腕を避けて脇腹を蹴り飛ばし、その勢いで軸がぶれて軽くよろけたところを二郎にぶつかる。
「大丈夫かよ、左馬刻さん。やっぱ飲みすぎじゃん」
「うっせ。さっさと畳むぞ」
二つのマイクを改めて起動する。一人ずつ蹴り飛ばしてもいいがこっちの方が手っ取り早い。背中合わせにナイフを掴んで囲んでくる連中を捌きながら鋭い一撃で息の根を止めるイメージで息を吐く。威勢のいい二郎のライムに重ねて刻み、手元を狙って突き出されるナイフを避けて僅かに乱れた呼吸をそのままフロウに織り込んでぶち上げる。自分のスタイルをぶつけて上手い具合にハマる瞬間。それぞれに踊っていたダンスのステップがピタリと揃う瞬間みたいな、「今、ここ」という瞬間。
脳の奥がスッとする。
二人とも敵に叩きつけるラップをやったはずなのに自分の内側も気持ちよくなる。回復系のラップを受けた時の感覚とも違う。懐かしくて嫌になる感覚だ。
アスファルトに金属の落ちる音と汚い呻き声が転がって刹那の快感は夢のように消え失せた。こっちはやっとエンジンがかかってくるところなのに叩きつけたバースの続きは返ってこない。これだから弱い連中とのバトルはクソだ。
二郎がしゃがみ込んでナイフを回収し、刃を折り畳み、コンビニの空き缶ごみ箱に放り込んだ。回収業者は迷惑するだろうが俺の仕事じゃないから放っておく。
「あー、余計な体力使っちまったせいで腹減った」
「テメェはさっきから夜食欲しがってたじゃねぇか」
うるさいからコンビニ店内に戻って酒とから揚げとスナック菓子を買った。ガキの躾も興が削がれたからナシだ。
二分ほどで店から出るとチンピラ連中はまだ足ふきマットに徹していた。踏み心地にも期待できない。跨いでマンションに向かって歩く。二郎は連中に同情心があるわけでもないのに少し立ち止まって、少し遅れてついてきた。
メインで居住しているマンションの一室に帰って二郎がテレビをつける。家でも録画している深夜アニメをリアルタイムでも見たいんだと。好きにさせて酒を開けていると音楽チャート番組が一郎の姿を映し出した。コンビニで流れたのと同じ曲だ。配信曲ランキングの上位に残っている限りこの手の番組は地雷だ。
さっさとチャンネルを変えろと言おうとした時、新譜の紹介が過去の楽曲紹介に切り替わった。The Dirty Dawg時代の曲だ。MVに被せて番組のナレーションが入る。昔の一郎と歌う姿が流れた瞬間にチャンネルが切り替えられた。テレビ画面の真ん中で灰色のスーツ姿の中年がニュースを読み上げている。それもニュースヘッドライン一件分にも満たない時間でテレビの電源ごと切られた。
「アニメ始まるまでに時間あるし、やっぱ家で録画で見るわ」
寝ちまいそうだし、と。ちっとも眠くなさそうな様子で言って買い込んだ食料を広げ始める。
「…………チッ。面倒くせぇな」
脳から直接こぼれ落ちた言葉にわざとらしく唇を尖らせる。
「うっせぇな。毎回話が難しくて伏線もいっぱい張られてっから集中して見ないとダメなんだよ」
クソアニメオタクがごちゃごちゃ言うがそっちじゃない。一郎のことで目くじら立ててるのはお互い様じゃねぇか。
一人のMCとしての山田二郎を知った当時、まだてんでガキで今よりずっと弱かった頃。一郎の背を追っていることを誇りとしてリリックで表現していた。マイクを握っている間だけでなく、取材に対しても兄への尊敬を繰り返し話していたような記憶がある。
それがいつ頃からかなくなった。一郎を尊敬するのをやめたわけじゃないし、俺の部屋に通ってくるようになっても相変わらず兄弟第一で生きている。そのくせ時々、過去のチームが上手くいってた当時の影を見つけると柄にもなく考え込みやがる。恐らく単純な嫉妬ってわけじゃない。当時の一郎と今の自分の立場が違うことは分かっているはずだし、何度も体で分からせた。それでも納得しない部分は夜景の見えるホテルに連れて行ったって解消しない。
触れないガラス越しの景色より寒くたって海風に浴びたいような奴の望みはきっと、自分の手でマイクを握って痛みを引き受けながらぶつかり続けなきゃ得られない。
まったく、金はかからないが手間のかかるガキだ。
〆
◆さまじろが付き合うまでのお話も書いてます!
よろしければハマブクロの犬シリーズ1からどうぞ
→掲載小説一覧
さまじろ小説の一部はWEB再録本として紙の本にまとめています。
詳細は下記ページでご確認ください。